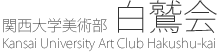関西大学は、1886(明治 19)年、大阪市西区京町堀の願宗寺を仮校舎に、関西法律学校として創立した。17 年間大阪市内を転々としたのち、1903(明治 36)年に江戸堀に学舎を建設。1905(明治 38)年には専門学校令による認可を受け、私立関西大学に改称した。
1906(明治 39)年、福島に移転。この福島学舎の建設工事中に学友会ができ、さまざまなクラブ活動が始まったとされるが、柔道や剣道、野球、テニスなどもっぱらスポーツ関係が中心で、美術部が存在した記録は見出すことができない。
この福島学舎時代、関西大学は「大学」と称していたものの、当時の文部省は帝国大学以外の公私立大学を大学として認めていなかった。しかし、1918(大正 7)年、文部省は一定の基準を満たす公私立大学に帝国大学と同等の資格を与える大学令を公布。関西大学は大学令に則した教育環境を整えるため、大阪市内から大阪府三島郡(現・吹田市)千里山に広大なキャンパス(現・千里山キャンパス)を建設し、1922(大正 11)年に大学の認可を受ける。
千里山に千里山に移転し、名実ともに総合大学として本格的な歩みを始めた関西大学では、豊かな大自然と充実した教育施設、大正デモクラシーの自由な時代気分を背景に、スポーツ関係だけでなく文化関係のクラブが相次いで創部される。そのひとつに美術部があった。
関西大学の関係資料に美術部が登場するのは、1924(大正 13)年 7 月 15 日付の『千里山学報』第 21 号における「千里山洋画展覧会」の記事が最初である。この記事は、6 月 27 日、28 日に第 14 号教室で開かれた関西大学洋画研究会主催の展覧会を紹介したものだが、この「関西大学洋画研究会」こそ、関西大学もその校史において認めてきた関西大学美術部白鷲会の前身である。
創部会員のひとりであり、この記事にも名前が登場する鳥海青児(1902 年~1972 年)は、関西大学卒業後、洋画家の道を歩み、1930(昭和 5)年に春陽会会員となった。1943(昭和 18)年からは独立美術協会会員として活躍。絵具に砂を混ぜた独特のマチエールで高い評価を受け、戦後は芸術選奨文部大臣賞、現代日本美術展最優秀賞、毎日美術賞を受賞するなど輝かしい栄誉に包まれた。まさに関西大学美術部白鷲会出身の美術家を代表する存在といえる。

記念すべき出発点 千里山洋画展覧会場にて 後列右から 3 人目が鳥海青児 1924 年(関西大学年史編纂室提供)